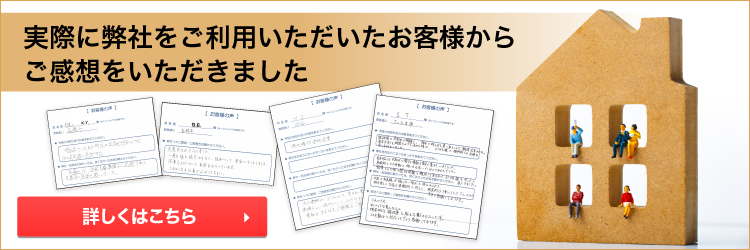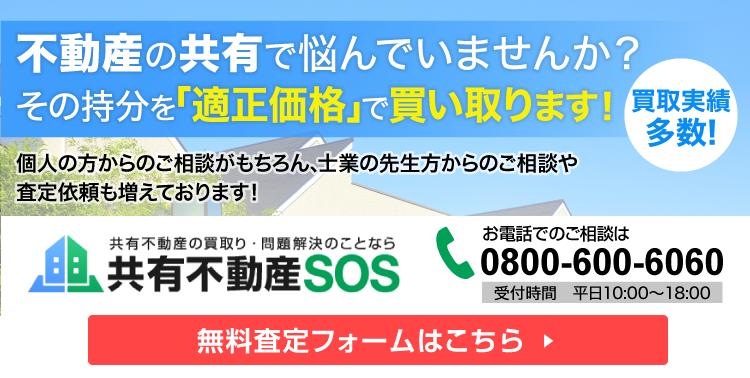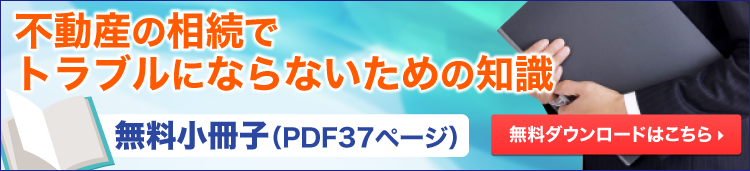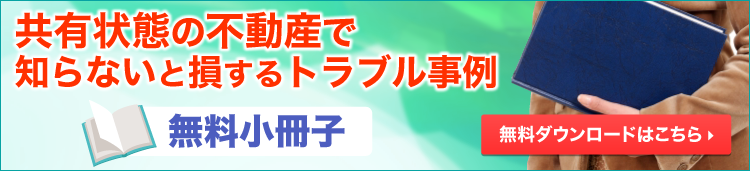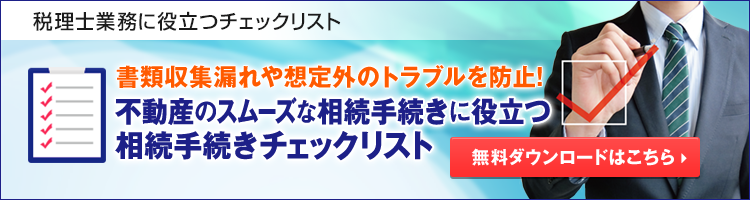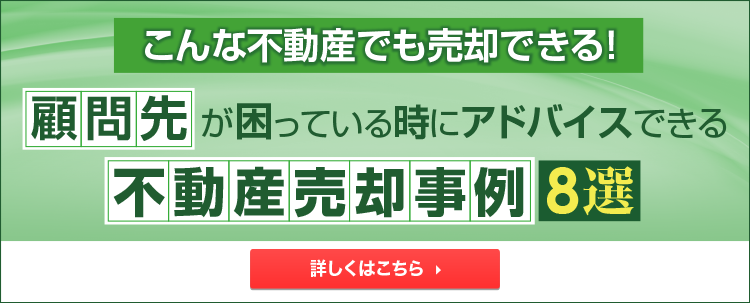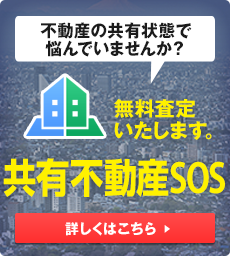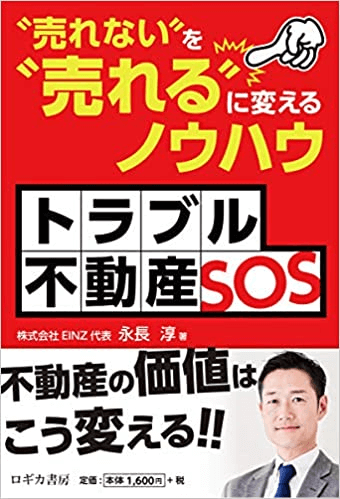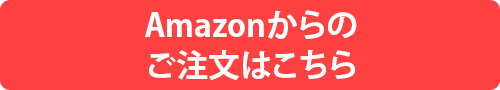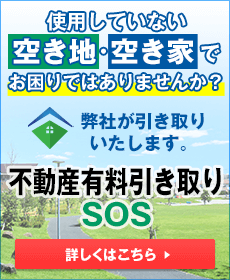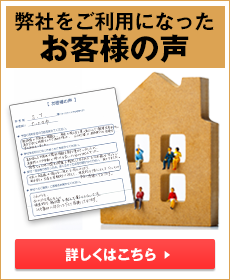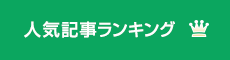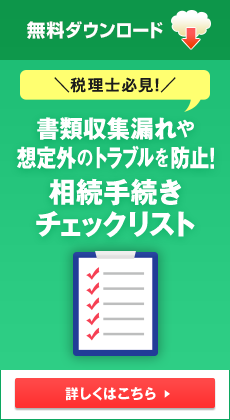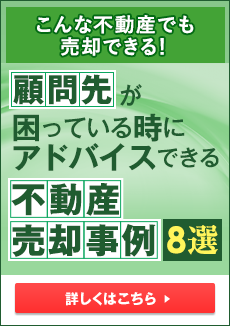契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?不動産の売主向けに解説

民法(債権法)が定める「契約不適合責任」は、あらゆる物品の売買に関わる人が抑えておきたい基本知識です。
とくに不動産の売主は、「売買価格が高額」かつ「代替物を用意しにくい」という性格だけに絶対に覚えておきたい知識といえるでしょう。
本稿では不動産の売主向けに、民法改正で規定された「契約不適合責任」と旧「瑕疵担保責任」との違い、契約不適合責任における4つの権利などについて解説します。
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?
契約不適合責任(瑕疵担保責任)を理解するときの必須キーワードに「瑕疵(かし)」と「特定物」があります。
「瑕疵」とは、傷物、欠陥、不具合などの意味です。
一方、「特定物」とは個性や特徴を備えたモノのことです。
一例は次の通りです。
- 不動産
- 中古車
- 骨董品
- 絵画
- 競走馬 など
改正前の民法(瑕疵担保責任)では、これらの特定物に「隠れたる瑕疵〈用語解説を参照〉」があった場合、買主が売主に対して以下を求められる内容でした。
これを「瑕疵担保責任」といいます。
- 原則、損害賠償請求
- 契約の解除(契約の目的が達しない場合に選択可)
※瑕疵が隠れたものでない場合(注意すれば明らかな欠陥など)、法的責任は認められないのが原則
瑕疵担保責任は「売主が無過失であっても責任を負う」とされていました。
特定物の売買契約を締結した時点で買主が知らなかった瑕疵、あるいは、買主が通常の注意力を働かせても発見できなかった瑕疵のこと。一例では、屋根に欠陥があることを知らずに建物を購入し、雨漏りが発覚したようなケースなど。
一方、改正後の民法(契約不適合責任)では、瑕疵という言葉自体は使われなくなり、売買の対象物が契約内容に適合していないときは、売主は買主に対して「契約不適合責任」を負うことになりました(特定物以外の売買も含む)。
▽瑕疵と契約不適合の違い
瑕疵 | 通常備えるべき品質・性能を有しないか又は契約で予定した品質・性能を有しないこと |
|---|---|
契約不適合 | 種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの |
引用:国民生活センター「気になるこの用語 第 20回」
なお、買主は契約不適合責任に基づき、以下の4つの権利を有します。
- 履行追完請求
- 損害賠償請求
- 代金減額請求
- 契約解除
契約不適合責任における買主が有する4つの権利
前項でお話した、契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについて改めて整理すると以下のようになります。
▽契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い
| 契約不適合責任 | 瑕疵担保責任 | |
|---|---|---|
| 改正前の民法か否か | 改正民法 | 改正前民法 |
| 特定物に限定されるか | 特定物を含む売買に適用 | 特定物の売買に限定 |
| どんな場合に売主が責任を負うか | 契約内容に適用しない場合(隠れたる瑕疵含む) | 隠れたる瑕疵がある場合 |
| 買主が有する権利 | ・履行追完請求 ・損害賠償請求 ・代金減額請求 ・契約解除 | ・原則、損害賠償請求 ・契約の目的を達しない場合は例外的に契約の解除 |
上記のように、契約不適合責任と瑕疵担保責任を比較すると、次の3つの大きな改正があったことが分かります。
- より幅広い売買(特定物以外)にも適用されることになった
- 契約内容に適用しない場合に売主が責任を負うことになった
- 買主はより幅広い権利を持つことになった
民法改正後の「契約不適合責任」で買主が有する4つの権利について確認していきましょう。
履行追完請求(改正民法562条)
1つ目の「履行追完請求」は、売買の目的物が契約に適合しない場合、それを補修したり、同等の機能や価値を持つ代替物に替えたりするなど、追加的な行為によって契約を完全に履行させる権利です。
ここでいう「契約に適合しない」とは、以下のようなケースを指します。
- (契約内容の)種類と異なる
- (同)品質と異なる
- (同)数量が異なる
注意点としては、土地や建物などの特定物に限り、代替物の引渡しは規定されていません。
つまり、不動産などの履行追完請求は「補修が原則」ということです。
この部分は、不動産の売主にとって大事なことですので覚えておきましょう。
代金減額請求(改正民法563条)
2つ目の「代金減額請求」は売主が追加的な行為(補修や代替物の用意など)を行わない場合、もともとの契約金額から相応分の代金引き下げを求められる権利です。
しかし現実的な問題として、売主は補修をしたい(履行追完請求を選びたい)、買主は代金減額請求をしたいと対立した場合はどのように考えればよいのでしょうか。
このようなケースでは「履行追完請求」を優先するのが原則です。
そして、買主が売主に対して履行追完の催告を相当期間行ない、これが実行されない場合は代金減額請求が行使できます。
損害賠償請求(改正民法564条)
3つ目の「損害賠償請求」は、契約の履行が遅れた場合などに損害賠償を請求する権利です。
前出の履行追完(追加的な行為)によって契約に適合する目的物が引き渡されるなどしても、「契約の期日よりも履行が遅れたこと(それによって損害があったこと)」を理由に、買主が売主に対して損害賠償請求をすることも可能です。
注意点としては、同じ損害賠償請求でも、「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」では次の違いがあります。
- 瑕疵担保責任の損害賠償:(売主の)無過失責任とされていた
- 契約不適合責任の損害賠償:(同)無過失責任ではなくなった
つまり、改正民法においては売主の故意・過失がなくても、目的物が契約内容通りでない場合、損害賠償の可能性があるということになります。
契約解除(改正民法564条)
4つ目の契約解除では、売買した目的物が契約に適合しないことを理由に「契約をなかったことにできる」権利です。
ただし、契約解除をするには、買主が「目的物が契約内容に適合しないこと」を知ってから1年以内に売主に通知する必要があります。
ただし、引き渡し時点で買主が「目的物が契約内容に適合しないことを知っていた」などに該当する場合は、「1年以内に売主に通知しなければならない」という権利行使機関の制限がかかりません。
なお、契約不適合責任に基づく契約解除は、一般的な債務不履行と同様に扱われます。
具体的には、買主が催告を相当の期間行い、履行されない場合は契約解除が可能となります。
不動産を売却する際の契約不適合責任のポイント
ここでお話してきたように、改正民法によって「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」となり、売主は4つの責任を負うことになりました。
見方によっては、売主の責任範囲が広がり、また売主と買主の解釈が分かれやすくなったとも言えます。
このことを踏まえると、不動産の売主はトラブルを回避するため、対象物件の性質や欠陥について売買契約書上でより明確にしておくことが重要です。
具体的に「どのような項目や表現が適切なのか」については、不動産を得意分野にする弁護士や、信頼できる不動産会社に相談するのが望ましいでしょう。
関連記事合わせてお読みください

第三者のためにする契約とは?取引時の売主・買主の注意点も解説
「第三者のためにする契約(いわゆる新中間省略登記、三為契約)」は、一般消費者にはトラブルが多いイメージもあるようです。 しかし、法的に認められている契約形態であり、十分な知識を持った売主と買主が……


傾いた家の売却はトラブルの元|傾きの許容範囲、売却する方法、価格への影響などについて
家を売却する際、売主は家屋の傾きに注意する必要があります。 傾きを放置し、売主に告知しないと、損害賠償請求などの深刻なリスクが生じる可能性があります。 ここでは、傾きのある家の所有者が気に……


地中埋設物の種類と費用は?杭が抜けないときの対処策なども解説
地中埋設物(コンクリ、木くずなど)を撤去する費用は、埋設物の種類や量、立地条件などによって大きく異なります。 その詳細と、地中埋設物がある土地を売却する際の告知義務や、地中深く埋もれている杭が抜……

新着記事最新情報をご紹介いたします

利用していない山林を所有していると、どのようなリスクがあるの?
-182views
高圧送電線が通っている土地(高圧線下地)とは?評価方法や売却時のポイン...
-153views
賃料値上げの通知時期のベストなタイミングは?値上げを実現するポイントも...
-136views
風呂場で亡くなった事故物件は告知が必要?売却前に知っておきたい基礎知識
-119views
賃料値上げの正当な理由は3パターンある!値上げが認められないケースも紹...
-114views
株式会社EINZ
150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-20-3
COERU SHIBUYA12F
TEL 03-6455-0546
FAX 03-6455-0547