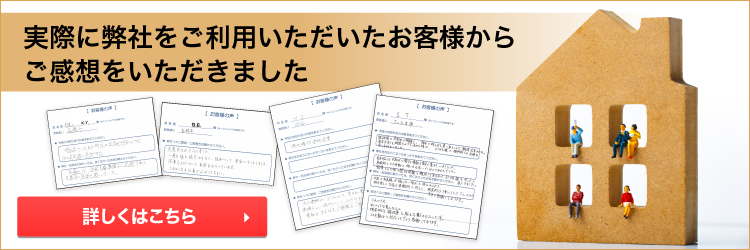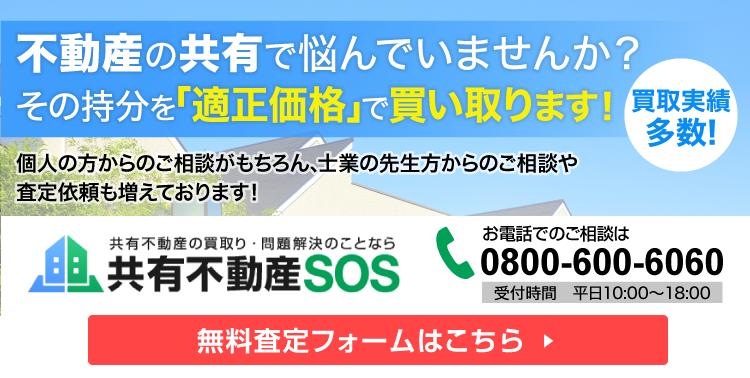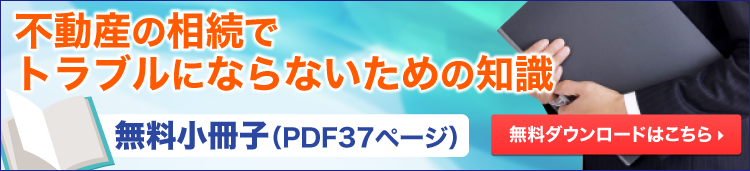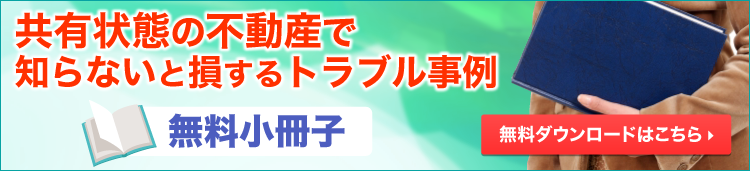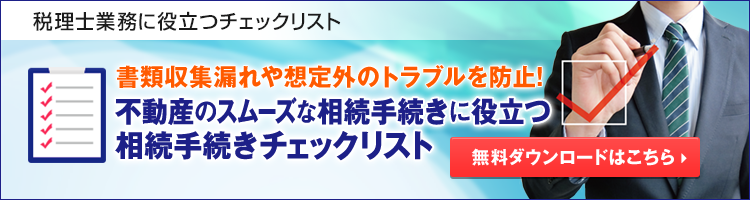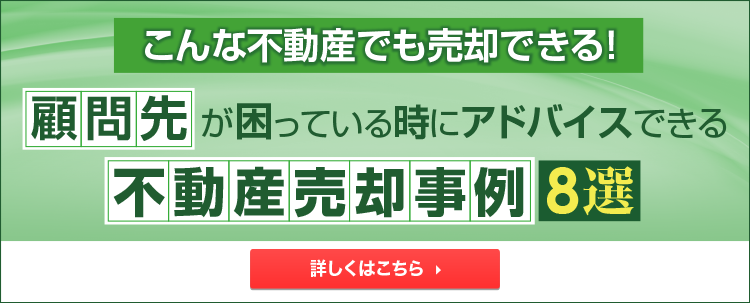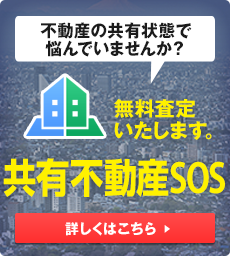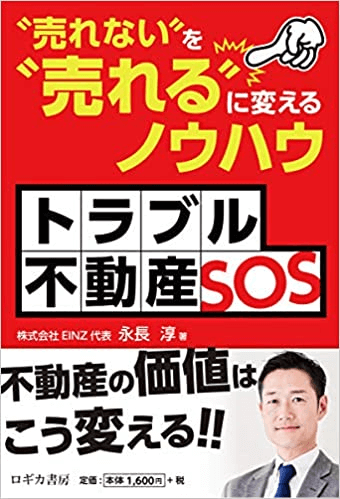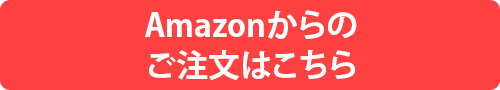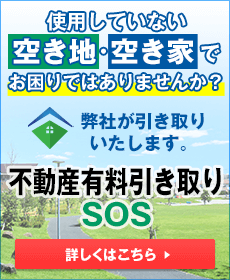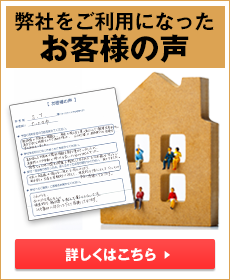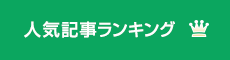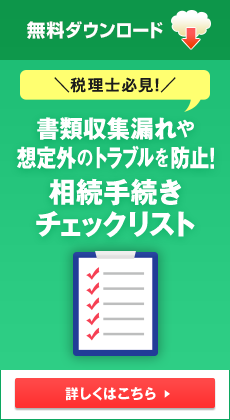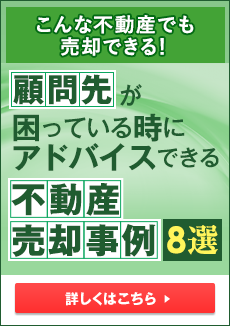高圧送電線が通っている土地(高圧線下地)とは?評価方法や売却時のポイントも解説

上空を高圧送電線が通っている土地(高圧線下地)を売却・処分したい方に役立つ内容です。
このコラムを読むことで、高圧線下地の定義・評価方法・売却のポイントなどを学べます。
高圧線下地の定義は?高圧線下地の問題点は?
はじめに、高圧線下地とは何か、高圧線下地にはどのような問題点があるかなどを整理しましょう。
高圧線下地とは、高圧の送電線下の土地のこと
高圧線下地とは、高圧送電線の下に位置する土地のことで、相場価格よりも評価価額や売却価格が低くなるのが一般的です。
しかし、上空を送電線が通っているすべての土地が高圧線下地になるわけではありません。
一般的に、「特別高圧の電線下にあること」そのことにより、「利用制約があること」に該当する土地を高圧線下地と呼びます(下記参照)。
▽低圧・高圧・特別高圧の定義
| 分類 | 電圧 |
|---|---|
低圧 | 直流:750ボルト以下 交流:600ボルト以下 |
高圧 | 直流:750ボルト超 7,000ボルト以下 交流:600ボルト超、7,000ボルト以下 |
特別高圧 | 直流・交流共に7,000ボルト超 |
参考:電気設備に関する技術基準を定める省令 「第1節/定義 第2条(電圧の種別等)」
高圧線下地の価値が低い理由は、「建築や植栽の制限」など
高圧線下地だと、相場価格よりも評価価額や売却価格が低くなるのは、下記のようなマイナス材料があるからです。
・建物の建造や植栽が制限される
・眺望が阻害される
・安全性で不安を感じる
・電波障害の可能性がある
・電磁波が健康に悪影響を及ぼすイメージがある
・送電線の騒音(風切音)がある
・鉄塔などの圧迫感 など
上記のうち、とくに「建物の建造や植栽が制限される」は、売却や買い取りの際に大きなネックになります。
具体的には、使用電圧によって制限の内容が変わってきます。
▽高圧線下地の土地利用制限の例
| 使用電圧 | 土地利用制限の内容 |
|---|---|
| 17万ボルト以下 | 高圧線の側方3メートルの範囲で建物の建造が不可(直下含む) *側方=左右の側面 |
| 17万ボルト超 | 直線距離3メートル以上の離隔で建物の建造が可能 |
参考:(公財)不動産流通推進センター「高圧線による土地利用制限リスク」
中でも、17万ボルト超の高圧線が上空を通っている土地だと事実上、建物の建造ができないのは厳しい制限です。
高圧送電線が通っている土地(高圧線下地)の評価方法
高圧線下地を売却・買い取り・相続する際は、相場よりも低く評価(補正・減価)されるのが一般的です。
補正・減価をするときに使われる主な指標は次の通りです。
この項の参考:国土交通省 近畿地方整備局「高圧線下地の土地評価について」
評価の基準1:地役権設定の契約
前提として、高圧線下地の利用制限は、電気事業者と土地の所有者の間で契約を結ぶことで有効になっています。
契約方式で一般的なのは「地役権」を設定し、登記を備えることです。
これにより、電気事業者は所有者などに対して利用制限を主張できます。
土地所有者への対価は、地役権設定時に支払われるのが通例です。
この対価を土地所有者がすでに受け取っている場合、土地を売却すると地役権の権利が次の所有者にそのまま引き継がれます。
そのため、その分を割り引いて評価するケースが多いようです。
逆にいうと、高圧線下地でもこのような契約を電気事業者と交わしていないなら、利用を制限する根拠がないため、減価割合は限定的ともいえるでしょう。
評価の指標2:土地価格比準表
「土地価格比準表」(監修:国土交通省)では、高圧線下地について以下を考慮しながら、適正に定めた率を使って補正(=一般的な土地よりも低く評価)するものとするとしています。
・高圧線の電圧の種別
・線下地部分の面積
・画地に占める位置 など
評価の指標3:離隔距離による減損
高圧線下地は、離隔距離によって建物の階数・配置・構造などが制約されます。
これにより、資産価値や市場価値が減損する可能性があり、その分を割り引いて評価する必要があります。
評価の基準4:その他の基準
これらの基準に加えて、「相続税財産評価基本通達」や「電気事業者の減価率の一例」などを高圧線下地の評価に用いることもあります。
高圧送電線が通っている土地(高圧線下地)の売却するときのポイント
高圧線下地を売却したいという人もいらっしゃるでしょう。
売却時のポイントは次の通りです。
ポイント1:高圧線下地であることを買主に理解してもらう
高圧線下地を売却する際にもっとも重要なことは、建物の建造や竹木の植栽などの利用制限があることを買主に十分説明することです。
不動産の売買においてトラブルを回避するためには、売主にとって不利な情報でも公開し、買主に理解してもらうことが大事です。
これは、高圧線下地に限りません。
過去には、高圧線下地であることを説明せずに土地を売却したことで、売主に対して契約解除や損害賠償請求を求めた訴訟にまで発展したケースもありますのでご注意ください。
ポイント2:地役権設定の内容を確認する
買主や仲介会社に対して、高圧線下地の情報を正確に伝えるためには、地役権設定の内容を確認しなければなりません。
この地役権設定を確認すれば、どれくらいの範囲で(例:高圧送電線から3.6メートルの範囲内)、どのような行為(例:建物の建築や竹木の植栽)が禁止されているかが確認できます。
地役権設定の内容が、不明または曖昧なときは不動産登記を確認しましょう。
全部事項証明書の権利部・乙区欄(所有権以外の権利に関する事項)を見ると、地役権設定がされているか否かが確認できます。
地役権設定がされていなくても、高圧線下地として利用が制限されている可能性もあります。なぜなら、地役権設定は義務ではないからです。
何らかの制限がある場合は、地役権設定のありなしに関わらず、買主に伝えるのが無難です。
ポイント3:売却価格の設定はケースバイケース
先にお話したように、高圧線下地は建物の建造や竹木の植栽などの利用制限があることから、売却の際、相場よりも価格が下がるのが普通です。
一方、売り出し価格をどれくらい下げると売却しやすいかはケースバイケースです。
極端にいえば、「割高でも高圧線下地が欲しい」という人が現れれば、相場価格で売却することは可能です。
売却の際は、複数の仲介会社の意見をヒアリングして、市場から求められる価格設定をすることが大事です。
ポイント4:買い取り査定は業者によって違う
なお、仲介でなく、専門業者の買い取りで高圧線下地を処分するケースもあるでしょう。
前述のように、高圧線下地には様々な評価基準があり、どれを用いるかは買い取り業者ごとに変わってきます。
高圧線下地の査定価格は、買い取り業者ごとに差がある可能性があるため、複数の業者へ査定を依頼して比較するのが賢明です。
処分できない高圧線下地は「有料引き取り」のご利用も
高圧線下地は、建物の建造や竹木の植栽の利用制限があるため、複数の業者に相談しても、売却や買い取りができないケースもあります。
活用しない高圧線下地を所有していても、固定資産税や管理費用がかさむばかり。
また、管理が行き届かずトラブルが起きれば、賠償責任を負わされる可能性もあります。
数十年単位で見た管理負担や相続を考慮すると、高圧線下地をこのまま所有しているよりも、「有料引き取り」を利用して処分したほうがメリットが大きいということもあります。
当社でも、不動産を有料で引き取るサービス「不動産有料引き取りSOS」をご用意しております。
不動産の処分にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
関連記事合わせてお読みください

第三者のためにする契約とは?取引時の売主・買主の注意点も解説
「第三者のためにする契約(いわゆる新中間省略登記、三為契約)」は、一般消費者にはトラブルが多いイメージもあるようです。 しかし、法的に認められている契約形態であり、十分な知識を持った売主と買主が……


傾いた家の売却はトラブルの元|傾きの許容範囲、売却する方法、価格への影響などについて
家を売却する際、売主は家屋の傾きに注意する必要があります。 傾きを放置し、売主に告知しないと、損害賠償請求などの深刻なリスクが生じる可能性があります。 ここでは、傾きのある家の所有者が気に……


地中埋設物の種類と費用は?杭が抜けないときの対処策なども解説
地中埋設物(コンクリ、木くずなど)を撤去する費用は、埋設物の種類や量、立地条件などによって大きく異なります。 その詳細と、地中埋設物がある土地を売却する際の告知義務や、地中深く埋もれている杭が抜……

新着記事最新情報をご紹介いたします

風呂場で亡くなった事故物件は告知が必要?売却前に知っておきたい基礎知識
-145views
高圧送電線が通っている土地(高圧線下地)とは?評価方法や売却時のポイン...
-143views
利用していない山林を所有していると、どのようなリスクがあるの?
-128views
賃料値上げの正当な理由は3パターンある!値上げが認められないケースも紹...
-109views
賃料値上げの通知時期のベストなタイミングは?値上げを実現するポイントも...
-107views
株式会社EINZ
150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-20-3
COERU SHIBUYA12F
TEL 03-6455-0546
FAX 03-6455-0547