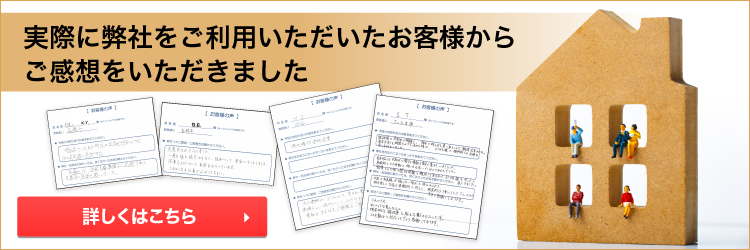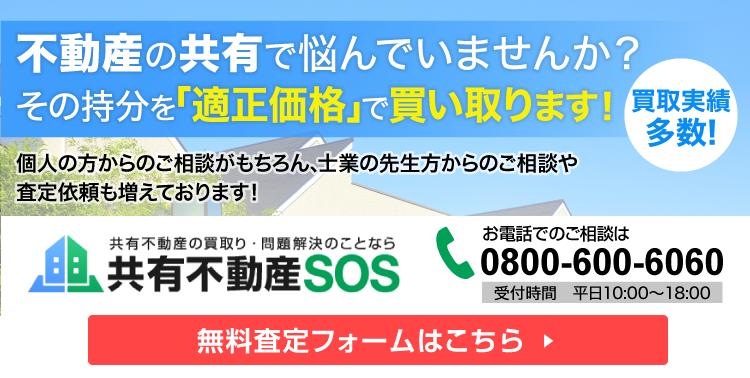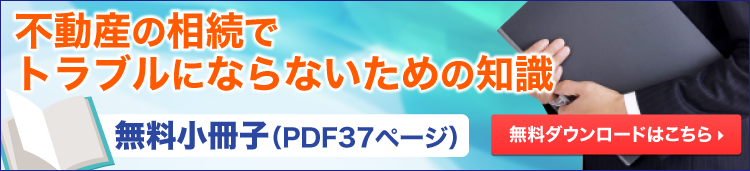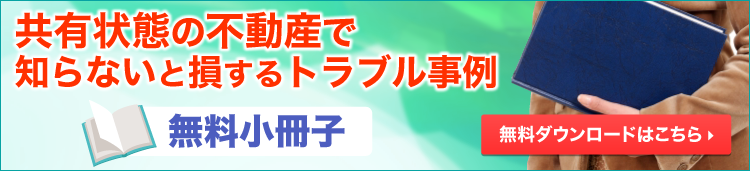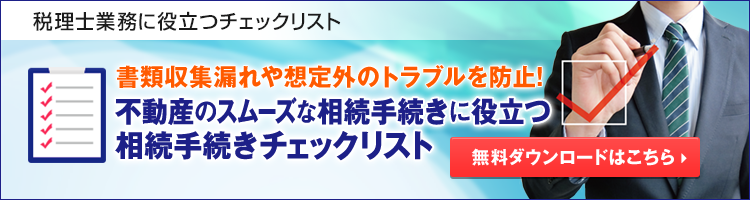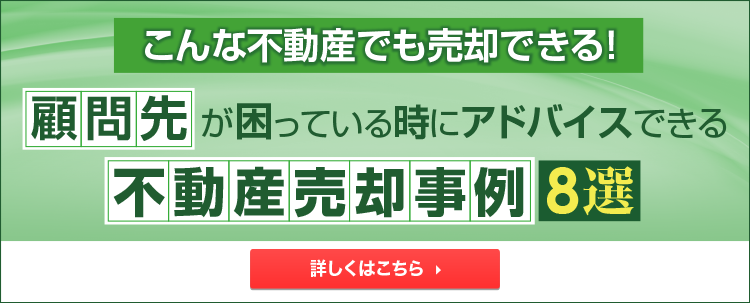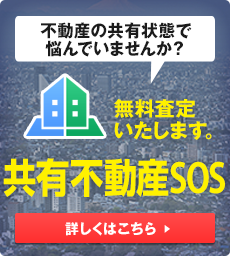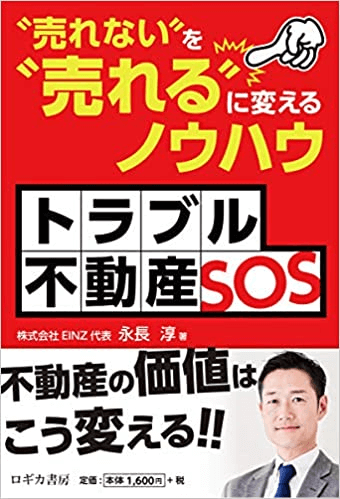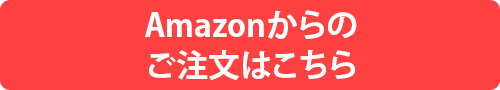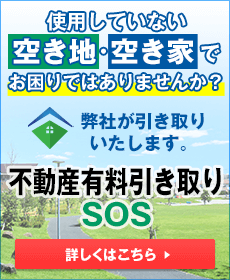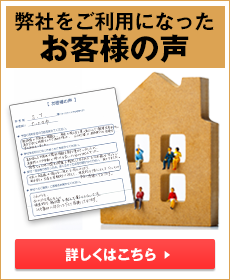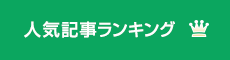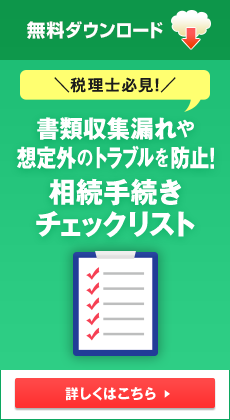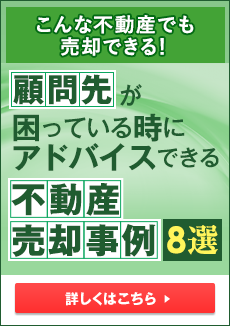相続土地国庫帰属制度とは?この制度のメリットは?

相続土地国庫帰属制度は、相続等により取得した不要な土地を手放せる新制度。法改正により2023年4月に始まりました。
この制度の内容・要件・メリットなどをわかりやすく解説します。
不要な土地を所有している人は必読です。
相続土地国庫帰属制度とは?対象になるための要件とは?
はじめに、相続土地国庫帰属法の内容、利用時の費用・要件などを解説します。
相続した不要な土地を国に引き取ってもらう制度
相続土地国庫帰属制度とは、相続等(売買や贈与は原則不可)で所有することになった不要な土地を、法務大臣(法務局)の承認を受けて国に引き取ってもらう制度です。
正確には「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます。
法律の施行前の段階で、すでに関連する相談が数千件寄せられていたようで、それだけ多くの方々が不要な土地の取り扱いに困っているということが伺えます。
相続土地国庫帰属制度の利用には、審査手数料と負担金が必要
相続土地国庫帰属制度は国の制度ということで、土地を無償で引き取ってくれるイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。利用時には、以下の審査手数料と負担金が発生します。
▽相続土地国庫帰属制度の費用とその内容
| 審査手数料 | 申請時に支払う 1筆の土地あたり1万4,000円 |
|---|---|
| 負担金 | 審査を経て承認後に支払う(承認された場合のみ) 10年分の土地管理費相当額を納付 宅地・田畑・原野などは面積にかかわらず20万円 *一部の市街地などは面積に応じて算定 *森林は面積に応じて算定 |
参考:政府広報オンライン『相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」』
この制度の裏側には、所有者不明土地の急増がある
相続土地国庫帰属制度が制定された背景には、いわゆる「所有者不明土地」が社会問題化していることがあります。
「所有者不明土地」とは、以下のいずれかの状態にある土地のことです。
・不動産登記簿を確認しても所有者がわからない土地
・所有者が確認できても住所や連絡先がわからない土地
所有者不明土地が、相続登記の未了などによって増加していることから、国は民法・不動産登記法を令和3年に改正し、相続土地国庫帰属法を制定する運びになりました。
所有者不明土地の総面積は、少し前は「九州の面積(約368万ヘクタール)に匹敵する広さ」と紹介されることが多かったのですが、現在では九州の面積を超え、国土の約4分の1を占めるまでになっています。
さらに2040年頃には所有者不明土地が倍増するとの推計もあり、まさに喫緊の課題になっています。
参考:法務省民事局「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」
相続土地国庫帰属制度の対象となる10要件
ただし、すべての不要な土地を国が引き取ってくれるわけではありません。
なぜなら、土地の所有者には、管理の責任と負担があるからです。
これは国も同じです。不要な土地を国が無条件で引き取ってしまえば、解体費・調査費・管理費などの負担が膨らみ、財政を圧迫する一因になりかねません。
具体的に、相続土地国庫帰属制度を利用するには、次の要件を満たす必要があります。
▽相続土地国庫帰属制度の対象の土地の10要件
1.建物がない
2.抵当権や賃借権などが設定されていない
3.通路や墓地などを含まない
4.有害物質で汚染されていない
5.境界が明らかになっている
6.勾配30度、高さ5メートル以上の崖がない
7.管理を阻害する車や樹木などがない
8.産業廃棄物などが地下にない
9.隣接地の所有者らと争いがない
10.防災措置の必要性や金銭債務の承継など過分の管理コストがかからない
引用:日本経済新聞 2023年4月27日付
これらの要件を集約すると、「整備や管理などのコストが最小限で済み、近隣とのトラブルなどリスクのない土地のみ引き取れる」ということになるでしょう。
ただし、注意したいのは今後、制度の中身が変わる可能性もあることです。
日経新聞では「法務省は運用状況を踏まえ、施行から5年をめどに見直しを検討する方針だ」と解説しています。
相続土地国庫帰属制度のメリットは?
相続土地国庫帰属制度を利用した際のメリットは次の通りです。
メリット:承認を受ければ 不要な土地を引き取ってもらえる
先にご紹介した要件を満たし、法務大臣(法務局)の承認を受ければ、相続等で取得した不要な土地を引き取ってもらえます。
これは「買い手がつかない」「自治体や近隣への寄付を断られた」など、いらない土地の処分に困っている方々にとって朗報でしょう。
メリット:業者に依頼するより安い費用負担で済む
不要な土地を処分する方法としては、「負動産の引き取り業者を利用する」という選択肢もあります。その処分費用の設定は業者ごとにケースバイケースですが、一例では「固定資産税の30年分」や「既定の料金+諸費用+30年分の管理費用」などが設定されています。
一方、相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、10年分の土地管理費相当額(大半は20万円)というケースが多いため、 業者に依頼するよりも安い費用ですむケースが多いでしょう。
ただし、不動産によっては境界を明らかにする費用など別途金銭負担が生じるケースもあるので注意が必要です。
メリット:原則、帰属後の責任は問われない
相続土地国庫帰属制度によって国に引き取ってもらった土地は、後日、申請時の調査では分からなかった問題が出てきても、帰属を取り消されたり、損害賠償を求められたりすることは原則ありません。
ただし、申請者が虚偽の内容で申請をしていたり、土地に問題があることを知っていて隠したりした場合は、その限りではないので注意しましょう。
ここでお話してきたようなメリットのある相続土地国庫帰属制度ですが、下記のようなデメリットもあります。
・審査手数料や負担金が発生する
・共有者全員で申請しなければならない
・購入した土地では制度が使えない
・審査にそれなりの期間を要する
デメリットについて詳しくは下記のコラムをご参照ください。
【合わせて読む】
相続土地国庫帰属制度とは?この制度のデメリットは?
要注意!不要な土地を放置するのはリスクでしかない
不要な土地の取り扱いで注意したいのは、相続土地国庫帰属制度の要件に該当せず、制度を使えない場合でも放置しないことです。
不法投棄物・草むらの火事・近隣とのトラブルなどの可能性があり、撤去費用や損害賠償が発生するリスクがあります。
「不要な土地でも、管理をしっかりしている」という人もいるかもしれません。
しかし、活用していない土地に管理費と固定資産税を払い続けるのはムダでしかありません。
活用策が見つからないのであれば、負動産は早めに処分するのが得策です。
まとめ:「相続土地国庫帰属制度」以外の土地を処分する方法は?
ここで見てきたように、相続土地国庫帰属制度にはメリットがある一方、数多くの要件があり、どんな土地でも利用できるわけではありません。
相続土地国庫帰属制度が使えない方は、以下のいずれかの方法で不要な土地を処分していくことになります。
1.売却(仲介)
不動産を買いたい人を仲介会社に探してもらい、交渉を行って売買契約を成立させる。
2.不動産業者の買い取り
買い取り業者が不動産の査定を行い、折り合いがつけば売買契約が成立する。
3.有料引き取り
負動産の所有者が引き取り業者に費用を支払って処分する。
大都市圏の好立地にある土地であれば、上記のうち、「売却」「買い取り」を選択するのがよいでしょう。
これに対して、地方の土地・山林・権利関係が複雑な土地などは「引き取り」が向いています。
当社でも、不動産を有料で引き取るサービス「不動産有料引き取りSOS」をご用意しております。
不動産の処分にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
関連記事合わせてお読みください

第三者のためにする契約とは?取引時の売主・買主の注意点も解説
「第三者のためにする契約(いわゆる新中間省略登記、三為契約)」は、一般消費者にはトラブルが多いイメージもあるようです。 しかし、法的に認められている契約形態であり、十分な知識を持った売主と買主が……


傾いた家の売却はトラブルの元|傾きの許容範囲、売却する方法、価格への影響などについて
家を売却する際、売主は家屋の傾きに注意する必要があります。 傾きを放置し、売主に告知しないと、損害賠償請求などの深刻なリスクが生じる可能性があります。 ここでは、傾きのある家の所有者が気に……


地中埋設物の種類と費用は?杭が抜けないときの対処策なども解説
地中埋設物(コンクリ、木くずなど)を撤去する費用は、埋設物の種類や量、立地条件などによって大きく異なります。 その詳細と、地中埋設物がある土地を売却する際の告知義務や、地中深く埋もれている杭が抜……

新着記事最新情報をご紹介いたします
株式会社EINZ
150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-20-3
COERU SHIBUYA12F
TEL 03-6455-0546
FAX 03-6455-0547